給水分担金は資金計画での注意点です
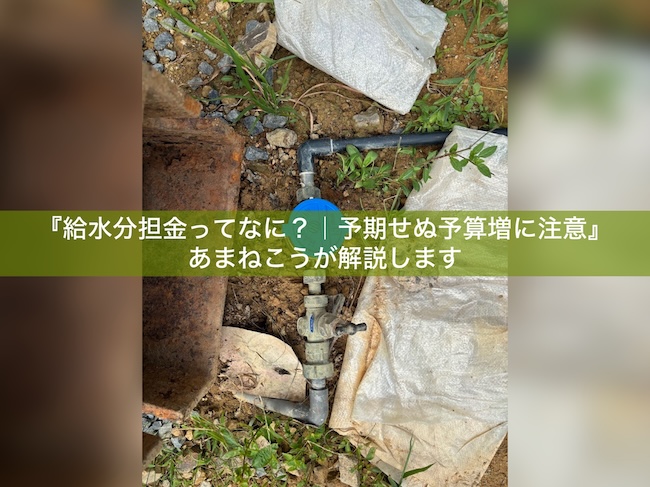
マイホーム、住まいづくりで一戸建ての建築を検討している方は、「資金計画書」というものを提案してもらっていると思います。
予算書、資金書、など呼称は様々です。内容は建物工事の見積書だけではなく、トータルで予算がいくら必要なのか、ということがわかる総額費用の書類です。
建築工事の見積書には、その建物を建築する際の水道工事は含まれていると思います。
しかし、水道工事でありながら見積書にほぼ含まれない水道工事代金があるんです。「給水分担金」です。
給水分担金とは
さて、給水分担金とは一体なんでしょうか。
これは簡単に書くと、給水装置(水道メーター)を設置する際に水道局(行政)に支払うお金のことです。
実は行政によって呼び方も違います。
京都であれば「(水道)加入金」と呼ばれます。給水分担金、メーター設置金、市納金、その他様々な呼び方がありますが、水道メーターを設置する際のメーター代金だとイメージしてもらうとわかりやすいと思います。
給水分担金(加入金)の費用の目安
この給水分担金、費用は一体どれくらい必要なのでしょうか。
京都市の代表的な口径の価格を紹介すると、
口径13mm:49,500円
口径20mm:99,000円
口径25mm:148,500円
となっています。一戸建てで口径25mmを超えることはほぼないと思います。現在では最低20mmを設置することが推奨されています。
ところで、費用はこれだけで終わりません。
水道メーターを設置する工事費用が発生
給水分担金(加入金)の目安はわかりました。しかし設置するための工事費用は別途必要になります。
古い建物の場合、メーター口径が13mmのお住まいがとても多いです。20mmに口径変更の場合は、前述の価格の差額と工事費用が必要なわけです。
ここで注意点があり、13mmを20mmに変更しても、道路から水道メーターまでの配管口径が13mmでは意味がありません。
もし引き込み管が13mmの場合は、道路を掘削して配管も20mmにする必要が発生します。
ということは、さらに工事費用は高くなります。50万円前後、行政によっては80万円前後、というような場所もあるんです。
給水分担金|見積書に記載されない

この給水分担金や、それに伴う工事費用は建物の見積書に含まれないことがほとんどです。
お客様からすると「なぜ?」と思うでしょう。
これは、水道メーターまでは水道局(行政)の管理管轄だからです。水道メーターから建物側への工事は建物の工事費用です。
道路から水道メーターまでは行政の管理であるのがややこしいところです。
まとめ|加入金を資金計画に算入しましょう

いかがでしょうか。
ほとんどの住宅会社さんや工務店は、工事の前に給水分担金関係を調査してお客様にお伝えしていると思います。
建物の見積もり金額以外に、「水道引き込みの工事費用が別途必要です」ということです。冒頭の資金計画書に書いてくれたら、なお親切ですね。
しかし、意外とこれが抜けるケースも多いようです。特に土地を買って家を建てるというような場合で、お客様自身で土地購入を仕切ってしまうような場合が要注意です。
住宅会社や工務店が、土地購入時点で「お客様もわかっているだろう」という誤解があった場合、建物引渡しの際に大きな金額が請求され、顧客と住宅会社でトラブルになる、ということもたまに聞きます。
いずれにせよ、建物の見積書に算入されない工事費用が存在しているということは知っておいて欲しいポイントです。
土地を買ったり、古家を購入して新築を建てる計画のお客様は、購入前に「水道メーターがあるかないか」「水道メーターがあれば口径は?」ということをチェックしてください。
京都市で家を建てるなら地元の工務店へ
京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。
たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。
そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。
土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。
この記事を書いた人

中川 高士
京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。
実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。
営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。
2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
【保有資格等】
・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者
・愛犬家住宅コーディネーター
・ホウ酸施工管理技士
・空気測定士
・向日市固定資産税評価委員会委員
「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。
住まいづくりで悩む方々へ
「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」
「いろいろ勉強してからスタートしたい」
いい家を建てたいなら、
いい住まいづくりをしないと失敗します。




