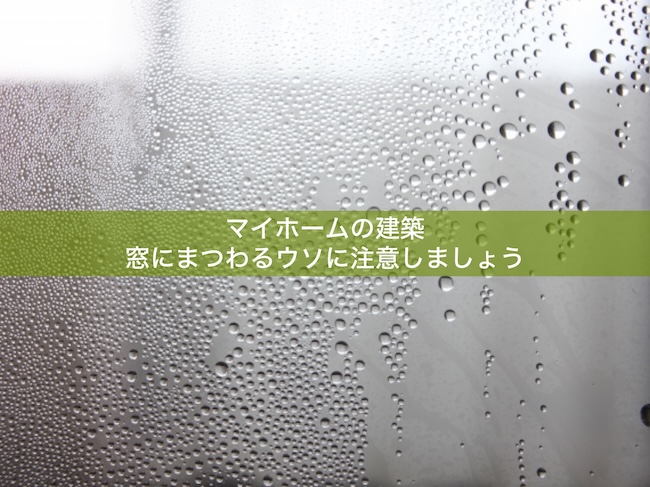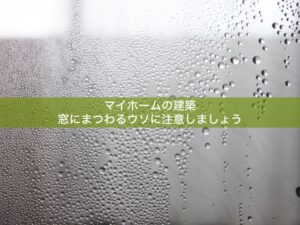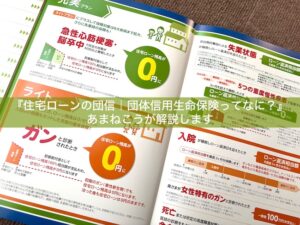結露とカビのコンビに悩む

「結露がひどい…」
「カビがすごくて…」
冬の寒い時期、梅雨時期、結露とカビのお悩みも発生する時期です。色々な対処法を試しても改善できないのでどうしたらいいですか、というご相談を受けました。
特に古いマイホームでどうしたら良いか。解説します。
家庭で試す間違った対処法
結露とカビでお悩みの方々は、それなりに対処されていると思います。ご相談の方は対策として、
「結露スプレー(アルコールスプレー)」
「結露テープ」
「湿気取り」
などを利用しているけれど大きく改善できないそうです。なぜでしょうか。答えは抜本的な解決になっていないからです。
これらは二次的な対処なので、まずは結露を発生させない工夫が先決です。
結露はなぜ起こるのか

カビの元にもなる結露。その結露はなぜ発生するのでしょうか。
これは小学校の理科でも習う飽和水蒸気量が答えです。空気が含むことのできる一定の水蒸気量を超えてしまった水蒸気(気体)が液体になる。
要するに「水」「水滴」になるわけです。
二次的対策が難しい理由
結露対策のアイデア商品はたくさんあります。ぜひ活用したいところなのですが、冒頭に書いたように一次的な対策ができていないと解決には及びません。
少し難しいですが理由を説明します。
空気が含むことのできる水蒸気は、空気の温度が高ければたくさん、温度が低ければ少なくなります。
ものすごく大雑把に書くと、1m3(立方メートル)あたり
室内空気温度25℃の時、約23g(湿度100%)
室内空気温度10℃の時、約9g(湿度100%)
以上となります。
仮に、上の条件で窓ガラスが10℃の時、室内が25℃であれば、
23g - 9g =14 g
という計算になり、14gの水蒸気が液体化、結露するわけです。
6畳の部屋、室内の高さが2.4mとした場合、
室内の空気の体積は約22m3(立方メートル)。
22 × 14g =308 g
308gの水が結露予備軍となるわけです。二次的な商品では追いつかない水分量です。
外気温や室内の無暖房の温度が10℃よりも低ければ、もっと結露の可能性は高まります。
結露に対する対策は

数字だけ見ると、結露の対策って出来なさそうに感じます。しかし、対策の方法は存在します。
結露は温度差のあるところに発生しますから、温度差ができるだけ無くなるように配慮すると良いわけです。
室内の表面・仕上げ材や、床材、家具などの表面温度と、室内の温度差が発生しないようにする。そういった仕上げ材や家具調度品を揃える。
壁の中など大きな温度差が発生する部分には水蒸気が入りにくいようにする。
水分量がそもそも多い水周りには一層の注意を払い上記対策を行う。
こういったことにより、一次対策が可能になります。
まとめ
いかがでしょうか。古いお住まいだと全てを叶えるには難しいことも多いでしょう。そういった時は温度計の湿度計をいくつか用意して対策も可能です。
寒い部屋と暖房している部屋の温度と湿度を可視化する。
外気温と室内温度の差を可視化する。
こういったことで、過剰に室内で湿度が高まらないようにし、結露のリスクを抑える意識で対策が可能になります。
リフォームなどで改善したい場合は、答えは一定ではありませんので上記のようなことを把握している住宅会社や担当者に相談すれば、個別に対策提案をしてくれると思います。
二次的商品に頼ったり、間違った知識で断熱リフォームなどをしないようにして欲しいと切に願います。
また、以前の記事で結露に関して似たテーマを扱っています。気になる人には参考になると思います。ぜひご覧になってください。
京都市で家を建てるなら地元の工務店へ
京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。
たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。
そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。
土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。
この記事を書いた人

中川 高士
京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。
実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。
営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。
2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
【保有資格等】
・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者
・愛犬家住宅コーディネーター
・ホウ酸施工管理技士
・空気測定士
・向日市固定資産税評価委員会委員
「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。
住まいづくりで悩む方々へ
「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」
「いろいろ勉強してからスタートしたい」
いい家を建てたいなら、
いい住まいづくりをしないと失敗します。