
こんにちは、京都市西京区で注文住宅を手がける「あまねこう」の中川です。
木造住宅を建てる際や、リフォーム・リノベーションで使用する木材を選ぶとき、
「杉やヒノキはシロアリに強い」
と耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな杉やヒノキの防虫・防蟻効果の真実について、科学的な観点も踏まえて解説します。
木材の種類とその特徴|針葉樹とは?
建築に使われる木材にはさまざまな種類がありますが、 柱や梁などの構造部分には主に「針葉樹」が使われます。
針葉樹とは、
- 杉(スギ)
- ヒノキ
- 松(マツ) などが代表的で、加工しやすく軽量であることが特徴です。
しかし「針葉樹=虫に強い」というイメージは、 実際には少し誤解を含んでいることもあります。
総ヒノキの家=シロアリに強い、は本当?

「総ヒノキの家にしてほしい」と言われた時代
中川が住宅業界に入った頃、 「建物すべてをヒノキで造ってほしい」と言われることが何度かありました。
ヒノキ=高級材、防虫効果が高い、という印象からでしょう。 たしかにヒノキは美しく香りも良いため人気がありますが、 実際には、一般流通しているヒノキがシロアリに極端に強いとは言えません。
ヒノキ・杉の耐蟻性(シロアリへの強さ)は“中程度”
「ヒノキはシロアリに強い」は、必ずしも正しくない
ヒノキや杉の耐蟻性は中程度とされており、 実際にはシロアリに食害されるリスクがあります。
科学的に見たヒノキの防虫性
かつて「ヒノキチオール」という成分が防虫効果のある成分として知られていましたが、 ヒノキチオールは主に青森ヒバ(ヒノキアスナロ)に含まれる成分であり、 一般的なヒノキ(ヒノキ科ヒノキ属)にはほとんど含まれていません。
また、現在の研究では、ヒノキ自体の香り成分や抽出液に対しても、 強力な防蟻性があるとは科学的に証明されていません。
つまり、「ヒノキだからシロアリに強い」というイメージは、 過去の誤解や混同に基づいたものとも言えるのです。
生きている木は強い、でも住宅に使うのは“乾燥木材”
山林のヒノキや杉がシロアリ被害を受けていないのは、 生きている樹木には水分や自衛成分による防御機能が備わっているためです。
しかし住宅に使用されるのは乾燥処理された「死んだ木材」。 さらに、人工乾燥によって天然成分も一部揮発・分解されてしまうため、 耐久性や防虫性は生きている木とは異なるのが現実です。
結論|どんな木材でも防蟻処理は必要です
杉やヒノキは、木材としては優れた性能を持っていますが、 「虫に強いから安心」と油断せず、 どの木材を使っても防蟻処理はしっかりと行うことが重要です。
あまねこうでは、自然素材の魅力を活かしながらも、 住まいの耐久性や安全性を高めるための正しい素材選びと処理方法をご提案しています。
気になる方は、お気軽にご相談ください。
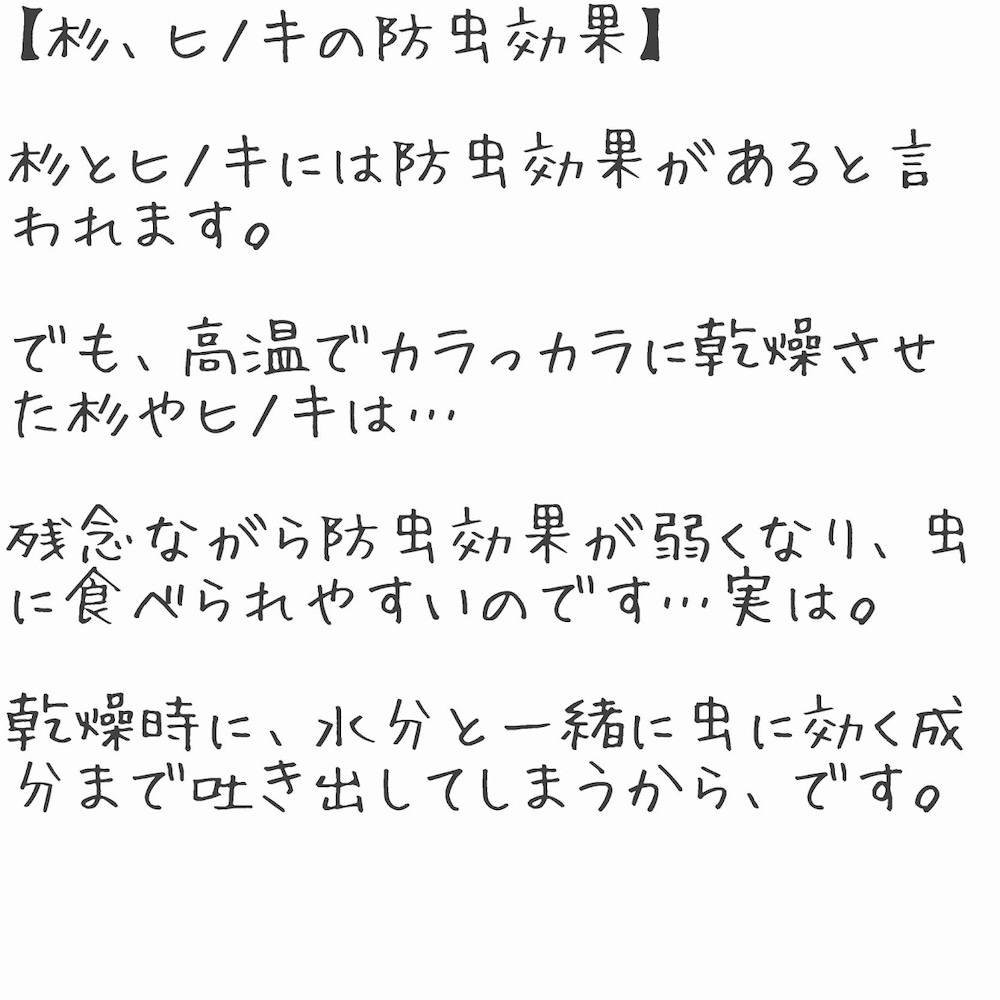
参考文献:東北森林管理局
参考文献:林野庁「科学的データによる木材・木造建築のQ&A」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/attach/pdf/handbook-24.pdf
京都市で家を建てるなら地元の工務店へ
京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。
たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。
そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。
土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。
この記事を書いた人

中川 高士
京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。
実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。
営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。
2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
【保有資格等】
・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者
・愛犬家住宅コーディネーター
・ホウ酸施工管理技士
・空気測定士
・向日市固定資産税評価委員会委員
「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。
住まいづくりで悩む方々へ
「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」
「いろいろ勉強してからスタートしたい」
いい家を建てたいなら、
いい住まいづくりをしないと失敗します。




