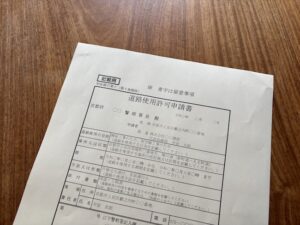はじめに|自然素材は「使えば良い」ではない?

近年、家づくりの現場で「自然素材を使いたい」という声が増えています。無垢材、漆喰、珪藻土など、身体に優しそうで見た目も美しい自然素材は確かに魅力的です。
でも、ただ使えば快適で健康的な住まいになるわけではありません。
「プロの視点で、自然素材を“うまく使う”とはどういうことなのか?」
本記事では、そのポイントを具体的に解説していきます。
自然素材の“良さ”を引き出すには、理解が必要

素材には“得意・不得意”がある
自然素材にはそれぞれ特性があります。
- 無垢材:湿度を調整してくれたりするが、反りや割れが起こりやすい
- 漆喰:調湿・防カビに優れるが、施工に技術が必要
- 珪藻土:においを吸着するが、水に弱くシミになりやすい
などなど、自然素材の特性を知らずに使うと、せっかくの良さが活かされないどころかトラブルの原因になりかねません。
暮らし方との“相性”が重要
例えば、湿気の多い場所で漆喰を選ぶのは理にかなっていますが、水がかかる場所に珪藻土を使うと表面が崩れたりシミができたりします。
「その家族の暮らしに合っているかどうか」まで考えるのが、プロの判断です。
自然素材の魅力を“デザイン”に落とし込む力

見た目の「統一感」が暮らしの心地よさに
自然素材の色や風合いは一点もの。私たちプロには素材の個性を読み取り、空間全体に調和させる設計力が重要です。
木、土、石。素材ごとに色や質感が異なるため、それを無造作に組み合わせると、ちぐはぐな印象に。
うまく使う=素材の個性を活かしながら、暮らしの中で自然に馴染ませる工夫ができるということです。
プロだからこそできる“メンテナンス”まで考えた提案
経年変化を楽しめる設計とは?
自然素材は、時とともに色や風合いが変化します。これは「劣化」ではなく、「育つ」過程とも言えるでしょう。
プロは、将来のメンテナンスや住み心地の変化まで見越した素材選び・配置を行います。
例えば、日差しが強く当たる場所で色の変化が大きくなりそうな時はその対策を、湿気がこもりやすい場所には調湿作用のある素材を。
その家に住む人が、10年後、20年後にも「選んでよかった」と思えるように設計することが、プロの腕の見せどころです。
おわりに|自然素材は「適材適所」で活きてくる

自然素材は、ただ「身体に良いから」「見た目がかわいいから」などで取り入れるだけでは不十分です。
- 素材の特性を知る
- 暮らしとの相性を見極める
- デザインと調和させる
- 将来まで考えて選ぶ
こうした視点があってこそ、「自然素材をうまく使う」ことができます。
家づくり・住まいづくりを検討している方は、素材だけでなく「どう使われるのか」まで見て選ぶよう心がけてください。
京都市で家を建てるなら地元の工務店へ
京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。
たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。
そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。
土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。
この記事を書いた人

中川 高士
京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。
実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。
営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。
2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
【保有資格等】
・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者
・愛犬家住宅コーディネーター
・ホウ酸施工管理技士
・空気測定士
・向日市固定資産税評価委員会委員
「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。
住まいづくりで悩む方々へ
「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」
「いろいろ勉強してからスタートしたい」
いい家を建てたいなら、
いい住まいづくりをしないと失敗します。