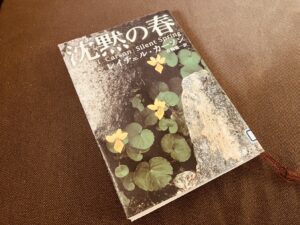みなさんこんにちは。
京都市で注文住宅を手掛ける「あまねこう」工事担当の中川です。
今回は、京都市南区の注文住宅現場で、基礎工事の工程のひとつである**「捨てコンクリート」**を打設しました。
狭小地ならではの施工とご近隣への配慮

京都市ならではの狭小地なので、施工時には作業スペースが限られ、資材搬入や作業動線にも気を遣います。また、工事の音や車両の出入りなどで、ご近隣の方々にご負担をおかけする場面もあります。
工事前には必ずご挨拶を行なっていますが、それでもなお温かくご理解くださる方ばかりで、本当にありがたいです。
おかげさまで現場はとてもスムーズに進行中です。
捨てコンクリートの役割とは?

「捨てコンクリート」とは、基礎工事の初期段階で地面に打設するコンクリートのことです。
見た目は地味ですが、その役割はとても重要です。
- 高さを平らに整える
- 墨出し(建物の正確な位置を示す線)を引くための下地
- GL(基準高さ)をもとに高さを再確認する
- 型枠や配筋(鉄筋組み)の安定した作業面をつくる
構造体ではないため鉄筋は入れませんし、厚みも5~10cm程度と薄めですが、この工程があることで後の作業精度が格段に上がります。
ところで「捨てコンクリート」とは?せっかくなので少しだけ解説いたします。
捨てコンクリート施工の流れと注意点

1. 地業(床付け)を整える
捨てコンクリート前には、地面を掘削し、基礎底面を水平に整えます。ここでの精度が悪いと、後の基礎工事全体に影響するため慎重に行います。
2. 厚みはおおむね5~10cm
捨てコンクリートは構造を支えるものではないため分厚くはしませんが、厚みを一定に保つことが重要です。これにより墨出しや型枠の設置がスムーズになります。
3. 墨出しを正確に
固まった捨てコンクリートの上に、建物の位置や柱芯を示す線を正確に描きます。この墨がずれると、建物全体の位置もずれてしまうため、職人の技術が試されます。
4. 天候を考慮する
コンクリート打設は天候の影響を受けやすい工程です。雨天時は表面が荒れたり乾燥不良が起こる恐れがあるため、施工日程は慎重に判断します。
💡 ポイント
捨てコンクリートは一見地味な工程ですが、基礎工事の精度を左右する大切な役割を持っています。
ここを丁寧に施工できるかどうかが、その後の家の耐久性や精度に直結します。
次の工程へ

捨てコンクリートが終わると、いよいよ外周部の型枠を組む作業に入ります。
これから基礎の形がはっきりと見えてくる段階なので、現場としてもワクワクする瞬間です。
京都市で家を建てるなら地元の工務店へ
京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。
たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。
そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。
土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。
この記事を書いた人

中川 高士
京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。
実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。
営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。
2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
【保有資格等】
・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者
・愛犬家住宅コーディネーター
・ホウ酸施工管理技士
・空気測定士
・向日市固定資産税評価委員会委員
「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。
住まいづくりで悩む方々へ
「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」
「いろいろ勉強してからスタートしたい」
いい家を建てたいなら、
いい住まいづくりをしないと失敗します。