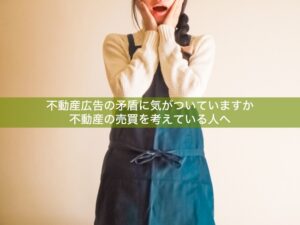京都市で家を建てる際のポイント

「景観条例」をご存知でしょうか。
京都市で家を建てる際や、リフォームなどで建物の外観に関する様々なルールが定められています。
驚くことに景観条例を知らない工務店もまだ京都には存在していて、必要な手続きなどが行われないと施主、お客様がトラブルに巻き込まれることになってしまいます。
京都市における景観条例を簡単に解説いたします。
景観条例とは|京都市
京都市は全国で初めて市街地景観条例を制定した街です。1972年に遡ります。過去には1930年代から景観に関する制度を定めてきた歴史を有する都市です。
そして2007年、新しい景観政策として今言われる「景観条例」が成り立ちました。
屋外看板、屋外広告の掲載場所や掲載するものを制限したり、
外観の色やデザインなどが地域の特性に合わせて細かく定められている、
などなど、その他も含めかなり細かく制定されているのが特徴です。
簡単に書けば、建物の外観に関する厳しいルール、ということになります。
景観条例は手続きが必要です|京都市
新しく家を建てる際の外観に関すること。リフォームの場合は既存の建物の外観や形質、簡単に書くとデザインや色、形(材料)などに工事が及ぶ際、手続きが必要になります。
定められている書類を揃えて、役所での相談や助言から始まり、事前審査、審査へと流れます。
不備がなければ、書類提出から3週間から1ヶ月くらいの期間が必要だと思って間違いありません。
外壁塗装などの際に注意|景観条例

特に注意が必要なのはリフォームでの外壁塗装などです。
塗装を承る工務店や塗装会社が、景観条例の申請をしたことがないというようなことが多くあるのです。
申請が必要だという意識がないため、悪気はないのですが条例違反になるのがお施主様、お客様ですので「景観条例」というもということはぜい知っておいてください。
また、地域によっては景観条例だけではなく、地域で景観保全に関して組織しているケースも京都市内では見受けられます。
筆者の経験でも、景観条例(京都市)はOKなのだけれど、地域組織でのOKがなかなか貰えなかったということがありました。
さらにはその逆もあったりします。
まとめ|京都市の景観条例

いかがでしょうか。
景観条例の細かい内容は、地域によって定められていますので興味のある方は調べてみるか、担当の工務店や住宅会社に尋ねると良いでしょう。
ここでのポイントは、「景観条例」という厳しいルールが京都市にはあるということ。
屋根や外観に関して制限があるということ。
特に外観に関していうと、
南欧風、プロヴァンス風などの一見華やかで可愛いというような外観にはしにくいというイメージを持っておいてもらっても間違いではありません。
新築の際は、建築確認申請の前に景観条例の審査を行うので、忘れていた、とか抜けていたということは無いでしょう。
リフォーム、リノベーションの際は担当する住宅会社や工務店の経験や知識に左右されるので必ず確認するようにおすすめします。
京都市で家を建てるなら地元の工務店へ
京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。
たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。
そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。
土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。
この記事を書いた人

中川 高士
京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。
実家が工務店という環境で育ち、幼少期から建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、28年以上にわたり幅広い建築会社で経験を積む。
営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまでを担い、建築の全体像を深く理解するに至った。
2023年に独立し、現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
【保有資格等】
・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者
・愛犬家住宅コーディネーター
・ホウ酸施工管理技士
・空気測定士
・向日市固定資産税評価委員会委員
「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを大切に、自然素材を活かした住まいづくりを提案している。
住まいづくりで悩む方々へ
「他社で質問しても今ひとつハッキリしない」
「いろいろ勉強してからスタートしたい」
いい家を建てたいなら、
いい住まいづくりをしないと失敗します。